システム研究センターでは無人化ロボットの実現に向けた研究を行っており、私は主に大玉トマト収穫ロボットの認識アルゴリズム・システムの研究開発に取り組んでいます。トマトの成熟度や形状、周りの障害物などをロボットが認識するためのアルゴリズムをロボットに実装し、それが収穫の自動化に有効か評価するというサイクルを繰り返します。年に数回実際のお客様の圃場(ほ場)でも試験を行っており、こうした実地での試験がアイデアに繋がることもあります。農業は労働人口の減少等の課題を抱えており、人手不足が続けばいずれ私たちの食生活にも影響します。トマトの収穫ロボットが実現すればほかの農作物にも応用することができ、農業分野の課題解決だけでなく、食の恵みを安心して享受できる社会の実現にも貢献できます。
農作物収穫ロボットのアルゴリズムを研究し
農業に新たな活路を開く
農作物収穫ロボットの
アルゴリズムを研究し
農業に新たな活路を開く
-
中央研究所 システム研究センターロボティクスG
工学研究科
未来ロボティクス専攻修了
2018年入社 -
夏迫 和也KAZUYA NATSUSAKO
現在の主な
仕事内容

ヤンマーで
働く魅力
自分が作ったアルゴリズムやシステムが圃場で設計通りの動きをしてくれたときは大きな達成感があります。学生時代はロボットを制作しても実際の現場で動かすことはありませんでした。一方、ヤンマーではリアルな現場の課題にフォーカスした研究を行います。お客様のところに出向き直接課題を伺ったり、組んだシステムを実際の圃場で試験できたりするのは、現場・現物・現実の“三現主義”を大切にしているヤンマーだからこそのやりがいだと感じます。また、ものづくりが好きな人が多いという社風も魅力です。私自身ものづくりやプログラミングが好きなので、上から指示されたことではなく、自分で課題を見つけ考え解決へ取り組んでいくサイクルは純粋に面白さを感じています。

大切に
している
想い
目先の課題解決にとらわれず、長期的な視点を持って研究に取り組むことです。5年、10年先を見据えて、新たな技術を構築することが研究所の重要なミッションだと考えています。すぐに結果を出すために短期的な解決方法を選びたくなりますが、結局はその場しのぎで全体の課題が解消していないという事態に陥りがちです。課題を解決する方法は、既存技術の中に答えがあるかもしれないし、誰にも発見されていない未知の仕組みかもしれません。たとえ時間がかかったとしても、将来性のある技術に着目し研究を行うことが大切だと感じています。それはロボットという形ではないのかもしれませんが、新たな解決方法を生み出しお客様に貢献できるよう、これからも日々技術を磨いていきます。

印象に
残っている
エピソード
新規プロジェクトのために圃場でデータ取りをさせていただいたときに、お客様から「ロボットなんか全然役に立たないし、いつまでもできないし、何も期待していない」と面と向かって言われたことです。ロボットの実用性の課題は大学などでも何度も言われていることなので分かっていたつもりでしたがグサっと来ました。実は学生時代、課題解決にはあまり興味がなく“技術さえできればいい”と考えていたのですが、その言葉をきっかけにお客様や社会の課題を解決したいと真剣に考えるようになりました。私たちの研究はお客様に使われて初めて価値を生むのであり、この経験が“どうしたら実用化できるのか・早く価値を提供できるのか”という研究視点の原点となっています。

ヤンマーを一言で言うと?
技術を好きな人がたくさんいる会社
得意なことは?
話を汲み取り、分かる言葉に言い換えてほかの人に伝えること
苦手なことは?
雑談などの話し役になること
休日の過ごし方は?
ドライブと読書
就活生の皆さんへ
就活でしか体験できないような貴重な機会を通して、自分のしたいことを見つけてください

 農業
農業
 トラクター
トラクター
 ジョンディア
ジョンディア
 トラクター作業機
トラクター作業機
 ガイダンス・自動操舵
ガイダンス・自動操舵
 田植機
田植機
 コンバイン・乾燥調製
コンバイン・乾燥調製
 ミニ耕うん機・管理機
ミニ耕うん機・管理機
 乗用管理機
乗用管理機
 ティラー・耕うん機
ティラー・耕うん機
 草刈機
草刈機
 無人ヘリ・ドローン
無人ヘリ・ドローン
 野菜機器
野菜機器
 大豆機器
大豆機器
 畜産・酪農機器
畜産・酪農機器
 運搬車
運搬車
 除雪機
除雪機
 水管理システム
水管理システム
 ミニショベル/油圧ショベル
ミニショベル/油圧ショベル
 ホイルローダー
ホイルローダー
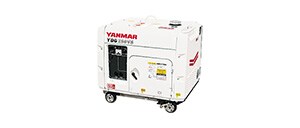 発電機
発電機
 マリンプレジャー
マリンプレジャー
 プレジャーボート
プレジャーボート
 漁船
漁船
 マリンエンジン
マリンエンジン
 海洋設備
海洋設備
 大形舶用エンジン
大形舶用エンジン
 高速主機関
高速主機関
 中速主機関
中速主機関
 舶用補機
舶用補機 SCRシステム
SCRシステム
 二段過給システム
二段過給システム
 電気推進システム
電気推進システム
 舶用デュアルフューエルエンジン
舶用デュアルフューエルエンジン
 金属ばね防振システム
金属ばね防振システム
 エネルギー
エネルギー
 GHP
GHP
 常用コージェネレーション
常用コージェネレーション
 非常用発電システム
非常用発電システム
 ポンプ駆動システム
ポンプ駆動システム
 カーボンニュートラル
カーボンニュートラル 廃熱ソリューション
廃熱ソリューション
 建設機械
建設機械
 キャリア
キャリア
 汎用関連機器
汎用関連機器
 投光機
投光機
 アタッチメント
アタッチメント
 純正部品
純正部品
 産業エンジン
産業エンジン
 立形水冷ディーゼルエンジン
立形水冷ディーゼルエンジン
 立形水冷ガスエンジン
立形水冷ガスエンジン
 空冷ディーゼルエンジン
空冷ディーゼルエンジン
 横形水冷ディーゼルエンジン
横形水冷ディーゼルエンジン


